トークセッション1「文化的『社会的処方』と共創の場」
2023年11月10日(金曜日)

- 日時:2023年7月29日(土) 13時15分〜15時00分
- 場所:東京都美術館 講堂
- 登壇者:伊藤 達矢(東京藝術大学社会連携センター特任教授)、稲庭 彩和子(国立アートリサーチセンター主任研究員)、中野 敦之(神奈川県民ホール館長付、事業課員)
- モデレーター:森 司
- 手話通訳:加藤 裕子、新田 彩子
社会とのつながりが薬になる:森 司
森:このセッションは「文化的『社会的処方』と共創の場」です。「社会的処方」についてですが、『社会的処方: 孤立という病を地域のつながりで治す方法』(西 智弘編著 2020学芸出版社)という本があります。ここでは、薬だけではなく体操や音楽、ボランティアといった地域活動などの社会とのつながりを処方することが「社会的処方」だと紹介されています。
このあと伊藤さんからは「社会的処方」のもう少し丁寧なお話と、文化的とはどのようなことか、お話しいただきます。稲庭さんからは、イギリスの事例と国の取組をお話しいただきます。中野さんには、イギリスでの体験と、神奈川県での事業についてお話しいただきたいと思います。
「共生社会」をつくるアートコミュニケーション共創拠点の取組:伊藤 達矢

▲伊藤 達矢さん
伊藤:東京藝術大学(藝大)で、「共生社会」をつくるアートコミュニケーション共創拠点という取組を進めています。国立研究開発法人 科学技術振興機構(JST)が出している、共創の場形成支援プログラム(COI-NEXT)の予算を獲得し、ウィズ/ポストコロナ時代を見据えて、国連の持続可能な開発目標(SDGs)に基づく未来のありたい社会像を描き、そこに辿り着くために必要な事業や研究を組み立てていくというプログラムです。
このプログラムでは、2030年が一つのテーマになっています。2030年を達成期限とするSDGs の目標は17個に分けられ、比較対照されて出てきた社会課題を全体で取り組もうというものですが、藝大ではサイエンス的なアプローチで積み上げてきたその先に、もう一度17個の目標を溶かしたり混ぜ合わせたりするアートのアプローチが重要だと考えています。そこで、“NEXT SDGsは「こころの豊かさ」へ”を掲げ、超高齢社会における孤独や孤立の問題に取り組んでいます。
複雑さを増す「超高齢社会における孤立や孤独」
藝大のミッションには、“芸術を以て社会に貢献する”ことが謳われています。しかし、そうした社会像を実現させようとするときに出てくるのが、孤立や孤独の問題です。2030年には65歳以上の方々が国民の3人に1人となる社会において、退職や身体的な衰えなどが原因となり、望まない孤独や孤立になる人が増えていきます。1日に15本のタバコを吸うよりも、孤立になっている状態のほうが健康への被害を及ぼすということが、研究で明らかになっています。
こうした問題を解決していくために、医療機関や自治体がそれを担い、テクノロジーやサービスが発達すればよいかというとそうではありません。社会的に様々な人が関心を持ち合い取り組み、それによって人々の幸福度が向上し、生産的活動に関われる人口が増えていくことが大切だと思います。
これを芸術のセクターだけで行うこともできません。溶け合わせたり混ぜ合わせたりすることが得意なアートが、まずは異質なものの接着剤のような役割を果たし、医療や福祉の機関、テクノロジー、コミュニティのネットワーク、自治体や海外の研究機関、NPOなどと連携し、総合的な拠点になっていこうとしています。
社会とつながる、自分とつながる「文化的処方」
様々な機関と一緒になりながら、この拠点で具体的にどんなことをやっていこうかとなったときの手法として、我々が一番注目しているのが「社会的処方」です。どういうものかというと、「私は眠れないんです」とお医者さんにかかった人がいます。「睡眠導入剤を足しておきますね」と薬を渡すのが医療としての処方です。でもその人の話をよくよく聞いてみると、2週間ぐらい外に出ていない、あるいは家族以外の人と話す機会がなく、結果的にQOL(Quality of Life:生活の質)が低いことにより眠れないという症状を起こしてしまっていることがわかりました。ならばその人が回復できるレジリエンスの高いコミュニティにつなげるというのが、「社会的処方」のあり方です。
「社会的処方」は、イギリスでは「ソーシャル・プリスクライビング(Social Prescribing)」と言います。日本語で社会というと、制度や仕組みという印象が強いのですが、Social Prescribingがしようとしていることは、制度や仕組みの外側にあるアートやカルチャーであったりします。そういうものが、その人をより回復させられる要素を持つのであれば、我々はそれを文化と捉えたいと思っています。
社会とつながる、コミュニティとつながる、人とつながるというだけでも大切なのですが、同時に自分自身と向き合う時間も必要です。そうしたつながりも含めて我々は、「社会的処方」を援用して「文化的処方」という呼び方で、これを推進しています。
「文化的処方」のコンセプトは心のハピネスへのアプローチ
WHO(世界保健機関)が定義する健康には、肉体的健康、精神的健康、社会的健康の3つがあります。この健康は、これまでは福祉や医療など、身体の側からアプローチされてきました。しかし、人の心のハピネスを上げていくことでも、この健康の3要素が上がっていくことが実はわかっています。ですが、その具体的な手法は、十分に研究されてきませんでした。
藝大では、ハピネスドリブンファクターで健康にアプローチをしていこうとしています。それが「文化的処方」のコンセプトです。クリエイティブな体験と、レジリエンスの高い地域の取組を結びつけ、それにテクノロジーを組み合わせて、その人が自分らしくいられる場や体験を「文化的処方」としようとしています。
ポイントになるのが、医療や福祉との連携です。多くの人は、自分の生活が立ち行かなくなってから福祉に頼りますが、それでは遅いと思います。福祉のあり方はもう少し遡って50代くらいの働いているうちから、一人ひとりに合ったケアと社会参加のデザインを考えていくことが、これからの社会に必要なセーフティーネットになっていきます。まずは地域の中で、いろんな形で世代や価値観を超えて楽しめる場づくりをしていっています。
人が人らしくあり続けられるための文化とこころの産業
我々の拠点の中でも一緒に取り組んでいるQDレーザさんやヤマハさんなど、様々な企業がいま、身体的機能を拡張するクリエイティブなテクノロジーを研究しています。例えばこのサマーセッションでも展示されているQDレーザさんの技術を用いたカメラは、ファインダーを覗くと、網膜に直接レーザが投影されるというものです。それにより、眼鏡などでは視力補正が難しかった方でも写真を撮ることができます。この発想が、「見える人と同じようにしてあげる」というところにはなく、その人の撮る写真はその人にしかできない表現として、人の価値や表現、尊厳がきちんと認められる関係性を作ることにあるところがすごいと思います。こうした関係性を推進するテクノロジーの可能性を、我々の拠点では「こころの産業」と呼んでいます。
2030年、NEXT SDGsにおいて、そこで開発されるサービスやテクノロジーが、本当に人を豊かに幸せにするのかという問いに立ち戻ることが必要だと思います。新しく出てくるテクノロジーとは、人が人らしくあり続けられるような良い出会い方をしていくことが重要ではないでしょうか。人がどのように社会の中で生きていくのか、テクノロジーや人と出会いながら、文化を介して社会とつながっていくことについて、私たちの共創拠点で考えていきたいです。続いて稲庭さんにバトンを渡します。
ウェルビーイングを育む「文化的処方」の国内外の事例から:稲庭 彩和子
稲庭:伊藤さんから共創の場のお話がありました。そのアイディアは突然出てきたわけではなく、その前10年間の東京都美術館での活動が、次のフェーズとしてつながっています。私からは、美術館やアートを介して社会にどのようにコミュニケーションを広げていくかという事例や考え方についてご紹介します。
東京都美術館×東京藝術大学で行われている「とびらプロジェクト」は、「とびラー」と呼ばれるアート・コミュニケータと一緒に、美術館を拠点にアートを介して人と人、人と物をつなげていくプロジェクトです。伊藤さんと共に立ち上げた当時から10年が経ち、毎年40名ぐらいの方が新たにアート・コミュニケータになるので、今では400名ぐらいのアート・コミュニケータがいるということになります。こうした美術館でのボランタリーな市民活動は、一般的には美術館にある素晴らしい名画や美術史的なコンテンツを普及していく活動だと捉えられることが多いのですが、私たちとしては、美術の普及ではなく、文化を介して人々や社会のつながりを形成し、コミュニティを育むソーシャル・デザインの活動だと思って取り組んできました。
2011年から始めて10年になる頃、国際社会全体の中でミュージアムの社会的価値が大きく変化してきていることがわかる出来事がありました。2019年の国際博物館会議(ICOM)において「ミュージアムは、多様な人々を迎え入れ、様々な声に耳を傾ける、民主的な空間です。私たちの過去や未来について、物事の前提や判断が本当に正しいか、なぜそうなのかを多角的に検討し思考する、対話のための場所です」という定義案が出されたのです。これは定義というより「ミュージアムはこうありたい」という理念のようなもので、大きな議論を呼びました。
この提案を見たとき、私はまさにとびらプロジェクトで実現したいことが書かれていると思いました。特にヨーロッパでは、ミュージアムの現場でそうした理念が育まれてきた経緯があり、特に欧州各国ではICOMによって提案されたようなコンセプトをもとに、いま文化施設が運営されています。
ICOM の定義案の最後には「全世界の平等と地球のウェルビーイングに貢献する」という言葉が出てきます。人々が地球も含めてウェルビーイングになっていく。文化を扱うミュージアムも地球全体と一体的になって「ウェルビーイング」に取り組んでいくことが大切だということです。
「ウェルビーイング」を日本語にすると「幸せ」と翻訳されることが多く、それだと「ハッピー」の訳とあまり違いがないのですが、ハッピーが一時的な幸せを指すのに対して、ウェルビーイングは、文字通り“Well=良い”と“Being=状態”を表していて、身体的、精神的、社会的に満たされている状態を指しています。社会的に健康というのは、その人の個人の尊厳が保たれている状態で、人とつながりを感じながら過ごせているということです。
美術館と「健康とウェルビーイング」の関係性
2023年3月末に、アート振興の新たな拠点として「国立アートリサーチセンター」が発足しました。全国に7つある国立美術館の機能強化をすると共に、美術館やアート関係の様々なセクターのハブとなって、アートをつなげ、深め、拡げることをミッションに設置されました。私はいまここで研究員として働いています。
ラーニングという部門の中に、「健康とウェルビーイング」という事業があります。美術館の旧来のイメージと「健康とウェルビーイング」というテーマは繋がりがないように思う方もいらっしゃると思います。でも、今急激に美術館の役割も社会の変化に伴って変わってきているのです。美術館は「芸術の殿堂」といったイメージであったものが、1980年代からは、社会の中でこれまでよりもアクセスの良い、学びの場、楽しむ場として求められ、変化してきた流れがありました。
1970年代、キャメロン・ダンカン(アメリカ 元ブルックリンミュージアム館長)という方が、「美術館はテンプルという神殿のような特権的な場所から、フォーラムのような人々が集まりそこから議論が始まっていく公平な場所になっていくのではないか」と唱えたときには、その考え方はかなり少数派でした。けれど50年ほど経ったいま、確実にその方向に動いています。
美術館の動きと共に、人の健康観も、その人を取り巻く社会的状況が健康を決定づけるという認識に変わってきました。また、人の尊厳、人権意識に関しても近年、ジェンダーやLGBTQ+や様々な面で話題になり変化してきています。こうした様々な分野の更新に伴い、健康やコミュニティ、人の尊厳を支える一つの技術として、アートの力を借りて「文化的処方」をしていくことが注目されています。
内面や感覚からつながりをつくるアートの作用
歴史を振り返ってみると、アートというものは私たちの歴史上にずっとあり、人間が社会を営む上で欠かせないものです。ではアートが私たちの社会にどのような重要性を持っているかというと、様々な意味で「つながり」をつくっていることだと思います。いわゆるテクノロジーのように、コミュニケーションをダイレクトにつなぐだけではなく、例えば自分の内面とのつながりがアートによって促進されることもあるし、他者と共通した感覚を一緒に持つことにアートが介在していたりします。
イギリスではまさにこの10年、アートが健康やウェルビーイングに寄与すると考える活動が広がってきました。超党派の議員連盟の方々が2017年に出した『クリエイティブ・ヘルス:健康とウェルビーイングのためのアート』というタイトルの報告書があるのですが、その表紙にはカルチャーと書かれたボトルから液体を飲んでいる人の象徴的な絵が掲載されています。
この報告書では、アートが人々の健康やウェルビーイングにいかに良い影響を与えるか、そこにどんな可能性があるかということが、様々なエビデンスや調査研究の数字で記されています。
イギリスには2,500もの博物館、美術館、ギャラリーがあり、そのうち約600施設で、健康と幸福の増進を目的としたプログラムが実施されています。日本には約5,000のミュージアムがあるので、今後こうした活動が活発になっていくのではないかと思います。
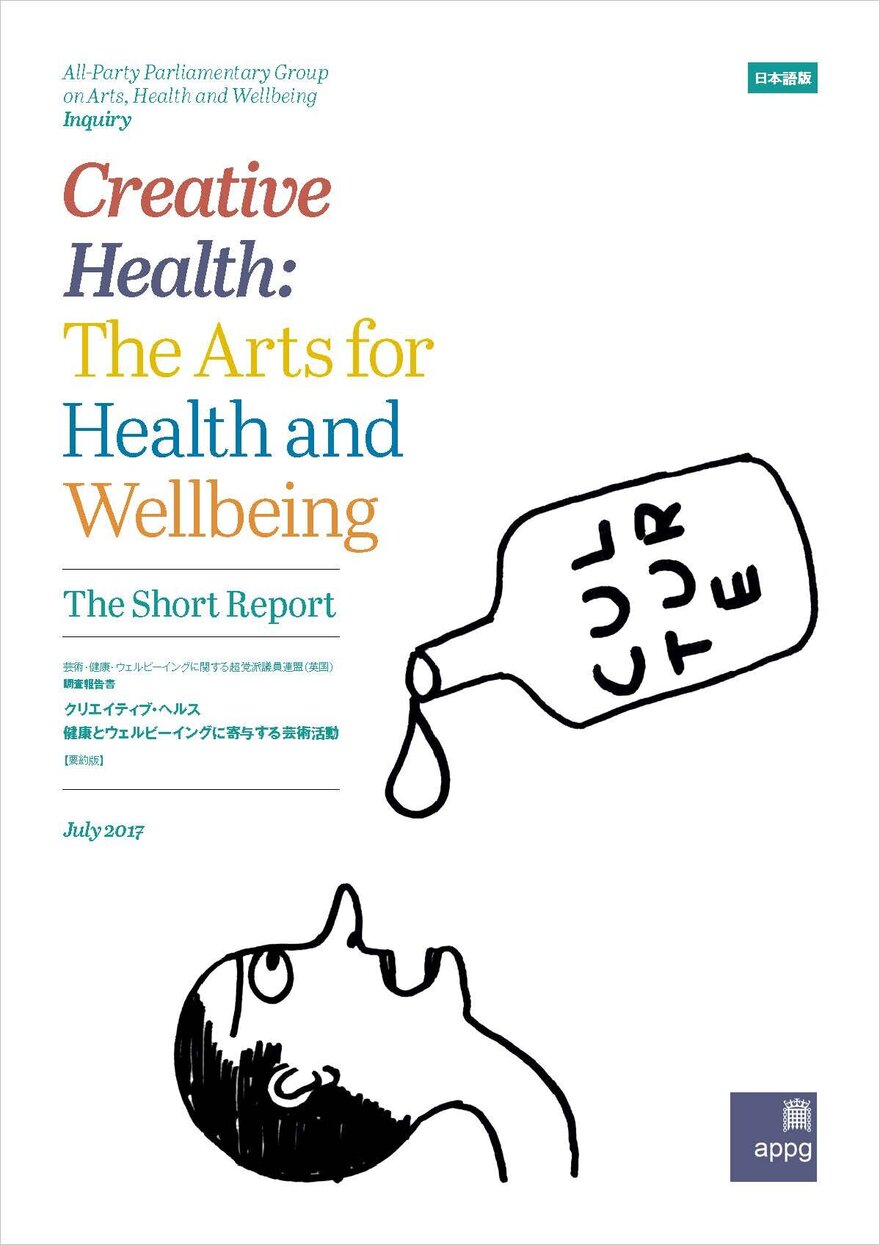
孤独担当大臣と政府横断的な孤独戦略
伊藤さんのお話にもありましたが、孤独の問題は、現代における公共保健上の最大の課題となっています。孤独な状態は、つながることを望んでも、そのつながりが億劫だったり負担だったり、なにか理由があって生じることがあります。そこで、直接つながろうよと正面からいくのではなく、作品やアート的な表現を介すことで、その人自身の内面との対話が起きたり、それぞれの背景にある文化を理解することでつながりの回路が生まれたり、有機的な形で人々がつながれる可能性があります。
イギリスでは2018年に孤独担当大臣というポストができました。日本でもこれを参照して、孤独・孤立対策担当大臣が2021年に誕生しました。イギリスに次いで世界で二カ国目となる任命です。
イギリスが策定した政府横断的な孤独戦略には、「かかりつけ医による地域活動やコミュニティ活動への仲介」という項目があります。この戦略では、かかりつけの医師が医療的な薬の処方箋を出すのではなく、例えば地域や社会とつながるような非医療的な方法の処方箋を提供します。その処方箋が出ると、リンクワーカーと呼ばれる専門家が当事者に寄り添い対話や共有を行います。その人がどのように社会とつながり、楽しみを見つけたり積極的に活動したりできるかを尋ね、例えばミュージアムのプログラムなどに一緒に参加するような、次のステップへと伴走します。これが先ほどから話していた、ソーシャル・プリスクライビング(Social Prescribing)です。直訳すると「社会的処方」となりますが、実際の意味としては、「文化的処方」と表現した方が適切かと考え、私たちの活動では「文化的処方」と言っています。
他にも「コミュニティカフェやアート空間などのコミュニティースペースの増設」、「長期的健康課題を抱える人を支援するボランティア活動試験プロジェクトの実施」などが孤独戦略として策定されています。今後日本においても、こうした「社会的処方」の視点が、政策の中に入っていくのではないかと思います。
つながりを感じることでウェルビーイングが育まれる
今年の1月に、国立アートリサーチセンターの調査のため、イギリスのロンドン、マンチェスター、リバプールに行きました。マンチェスターは、クリエイティブ・ヘルスの取組が進んでいる都市として知られています。
マンチェスターの市立美術館の分館である「プラットホール」は元は衣装博物館だったのですが、現在はリノベーション中でコロナ禍にも「社会的処方」の活動が積極的に行われたそうです。取組の一つとして「コレクション・チャット」というプログラムがあって参加者は、自分が興味を持ったコレクションを選び、それを見ながらおしゃべりをします。このアプローチは、学芸員が説明をするのではなく、参加者が物をよく観察し、自分の考えや記憶を引き出しながら話をしていきます。
イギリスの担当者は、この活動によりウェルビーイングが高まる効果があると言っていて、それは端的に言えば「ビロンギング(Belonging)」という言葉で表されると言っていました。「ウェルビーイングは、自分の属する場所やつながりを感じることで形成されるものであり、活動を通じてビロング(所属感やつながり感)が強化される」のだと。自分のいる場所につながりを感じている、それがウェルビーイングではないかということでした。こうした活動がZoomやリアルな場の両方で継続的に行われ、「社会的処方」の事例となっており、このような事例がイギリス全体で広まっています。
神奈川県とロンドンThe Albany(オルバニー)の事例から:中野 敦之
中野:県立の劇場である神奈川県民ホールで、館長付という立場で働いています。館長は県の文化顧問を務めているため、様々な案件が降ってきます。そうした突発的に起こることや、館の外で行うような事業に対応する人間がいないということで、僕が劇場スタッフとしては少し特殊なこの職域に任命されました。これまで野外での公演や企画運営をずっとしてきて、アウトドア系が得意技なんです。
屋外で行うアートの事業をしていると、街場に切り込んでいく楽しさがあります。街の人の元へ一生懸命通ったり、一緒に飲み食いしたりしながら、いろんな応援をもらえる喜びをたくさん体験してきました。
2017年度から神奈川県は、文化事業を横浜に集中するのではなく、県内全域に飛び出して盛り上げようと、全県展開事業を始めました。子どもたちのための演奏会をしたり、50人集まったら公演大成功という小さな町を訪ねてオリジナルの作品製作と発表をしたり、県内各地でイベントをしてきました。
ダウン症の青年たちの表現にも出会いました。福祉施設に「芸術劇場や公共の仕事です」と切り込んでいくと、初めは信用されません。そこで僕は本気であることを証明するために、向こうのイベントをお手伝いしたり、イベント会場がないというときには場所を提供したり、スタッフ会議にもレギュラーで参加してニーズを聞きながら、本当に有効なイベントとは何かを探りました。こうした活動をきっかけに、2018年から「共生共創事業」を立ち上げました。高齢化対策、障害のある方との協働、子ども、在神奈川の外国の方と創作活動をする事業です。
横須賀市・綾瀬市・小田原市にシニア劇団をつくり、横浜を拠点とするシニア向けダンスワークショップを開始しました。これは各地に出張しています。
福祉施設の特性を活かした作品も創作しました。その施設だからこそできるものを作ろうと、お弁当づくりとダンスをテーマに、振付家にも入ってもらって映像作品も作りました。
劇場は多様な人たちと日常的に関わっているかという問い
しかし、僕はこれでいいのかと問い続けています。というのは、福祉施設に行くといっても、なかなか劇場の全職員が参加というわけにはいきません。劇場が多様な人たちと日常的に付き合っているかと考えると、なかなか地に足がつかず、相手の事情を汲み取れていないのではないかと思うのです。
劇場スタッフの人間力も足りません。例えば神奈川芸術劇場は開館して10年ほどの綺麗な劇場ですが、ホームレスの方が劇場ロビーにあるLEDビジョンのニュースを観にきます。そうすると、ある劇場職員は警備員に電話してどいてもらうんです。いろんな人に劇場に来てほしいと言っているのに、そういうことが起こっています。
僕としては、誰にでも劇場を応援してもらいたいし、劇場を使って楽しんでもらいたいのに警備員に連絡するのは、反劇場的なことだなと感じます。ホームレスの人がいることで他のお客様が来にくくなるというのもまた事実なので、そうしたときに劇場職員が挨拶をして、少し端のほうに移動してもらうようなことができる必要があると思うのです。こうした能力は、面倒だけど素晴らしいものをつくるアーティストと付き合う能力ともイコールだと思っています。
コロナ禍もあり、劇場のファンは年々減っているように思います。自分が面白いと思って惚れ込んで働いている場所だからこそ、もっと拡めていきたいです。
生き生きした劇場、ロンドンThe Albany(オルバニー)との出会い
文化庁の令和3年度新進芸術家海外派遣制度で、ロンドン南東部にあるThe Albany(オルバニー)という劇場に研修に行きました。貧しく、治安も悪く、移民の多いルイシャム区のThe Albanyなら、疑問の答えが見つかるかもしれないと思ったためです。
The Albany は平屋2階建てで、客席数150席という楕円形の小さな劇場を持っています。面白いところは、劇場建物の一部が長屋みたいな建物になっていて、ここに芸術創作のための様々な事務所が入っていることです。劇団やダンスカンパニー、高齢化対策や子どもや障害のある方や移民に向けた取組をしている団体、さらにラジオ局や地域の商店街連合会の事務局まで入っていました。発表の場としてはもちろん劇場も使いますし、さらに街なかでのイベントも多い。それを各カンパニーがどんどん勝手にやっていく、生き生きした劇場です。
神奈川県の財団は神奈川県民ホール、神奈川芸術劇場、神奈川県立音楽堂の3館を運営していますが、The Albanyも3館を運営しています。でも運営している内容が全く違って、図書館、集会施設、学童、広場などです。学童運営のノウハウは、キッズプログラムを劇場でやるよい知見になると思いました。都心に近いところにも小さな劇場があり、そこには図書館、集会センターがあります。とても合理的だと思いました。
心をわしづかみにする創作と集いの場としての劇場
The Albanyでのワークショップを紹介します。シニア向け美術ワークショップでは、手芸や押し花、歌謡曲の合唱などがあり、その活動は日常的で、内容的にも簡単に参加できる、間口が広いのが特徴です。移民の人が多いので、アフリカのジャンベワークショップというのもありました。スパイスを組み合わせたオリジナルの紅茶づくりワークショップもあり、これは、スパイスが穫れる国から移民してきた人たちが自分たちのルーツに触れているんだと思いました。半期に一度はTea Danceといって、様々なレギュラーワークショップの成果発表をしながら、作ったお茶を飲んで踊るという企画もありました。
難しい創作になってくると、ショッピングモールでの移動型演劇もあります。自分が参加したのは引越しをテーマにした演劇で、それぞれの体験を募って演出作家がその体験談をまとめてシニアたちが演じるというものでした。モール内のいろんなところをウロウロして演じていくと通行人が強制的に立ち会うことになって面白かったです。
障害のある方たちも、クラブイベントが大好きです。成人していたら当然お酒もありです。こういう日はスタッフと警備員を多めに投入し、事故が起こらないよう注意をしていました。爆音が苦手でパニックになるという人は、庭で静かにラジオ放送をしていることもありました。
保護者のために、無料でマッサージを受けられるサービスもありました。みんながクラブイベントで踊り騒いでいる時に、少し離れた部屋でマッサージを受けられます。劇場でのイベントがあるおかげで束の間、日々の緊張から親御さんたちが解放される。この発想を見たときに、劇場が人々の心をわしづかみしにいっているサービス精神と想像力に唸りました。まだ自分は勝てないなと反省しました。
街なかで何度もクラブイベントを仕掛け、夏休みには学童の遊具施設でファッションショーをします。なかには、青年たちが植樹をしながら、環境問題を訴える自作の詩を朗読する催しのような実験的なイベントもありました。
劇場のシンポジウムは月曜の朝に行われました。それには理由があって、近所のお母さん方も保育園に子どもを預けたら来てほしいということでした。ロンドンは物価が高く、クロワッサン1個400円ほどするのですが、クロワッサンと紅茶とコーヒーの無料提供もありました。飲み食い目当てに来て、ついでに話を聞いてくれればいいというディレクションです。
劇場の壁面には、シニア向けワークショップの参加者で、ジャマイカから40歳の頃に渡ってきて現在97歳という、最高齢の参加者がフォーカスされたビジュアルがありました。こういう人たちのための劇場なんだと、街に向かって全身で訴えているような劇場でした。
巨大なメッセージを劇場に込めて
神奈川県民ホールは、老朽化のため2025年3月末に休館することが発表されています。神奈川県の方針はまだ定まっていませんが、現場としては、新しい劇場を造りたいと願っています。どんな建物になるか、それこそ神奈川県の文化政策として巨大なメッセージになるはずです。休館中にいかに神奈川全域の人たちと出会って状況を把握できるか、イベントを発信できるかで、未来型の県民ホールになるかどうかが決まると思っています。こういう人たちに喜んでもらいたいんだ、世の中にはこういう人間の状態がありうるんだと、出会いを求め、生活を知ることは、巡り巡って、これまでやってきたオペラやバレエなどのハイカルチャーも鍛えていくはずです。
多様な方向からつながり共鳴する「文化的処方」へ
森:「文化的『社会的処方』と共創の場」という輪郭が見えたところで、最後に一言ずついただきたいと思います。
伊藤:豊かになっていく社会のあり方で大事なのは、どんなときにどんなふうに誰と出会っていくのかです。「社会的処方」について最近考えているのは、個人だけではなくて、地域に対して提案していくということです。するとそこがレジリエンスの高い地域になっていき、暮らしている人たちの健康やウェルビーイングも上がっていきます。そうした取組を、藝大も率先してやっていきたいと思っています。
稲庭:文化セクターや大学が動けるような体制を作っていこうとするときに、世の中にあるいろんな知見を持つ方々が、少しずつ共鳴し合ったり、手をつなぎ合ったりしていくことが、力になるのではないかと思います。今日この機会に集まった方々ともシェアやつながりを通して力強く次のフェーズを作っていけたらと思います。
中野:私が最後に言いたいのは、私たちは追い込まれているということです。「文化的処方」と言うと、社会課題を解決できますよ、という余裕を感じる。でも実態は、私たち劇場は切迫しており、生き残りをかけて様々な事業を行っているのです。だからこんなふうに役に立てますよと、地域に向かって懸命に売り込みをかけているというのが自分の実感です。そうでないと劇場が社会とつながっていけず、いまに人々に必要とされなくなっていくだろうと危機感を持っています。芸術文化や文化施設が皆さんの社会や生活の実態とダイレクトにつながり根を張る作業を急いでいます。多くの人に劇場を支持してもらえるよう、土台を築きたいと考えて行動しています。
森:中野さんの最後の言葉からは、我々が言ってきた「社会的処方」という形で社会参加すること以外に、もう一つ別に、美術館や劇場側の社会参加も考えなければいけないよね、という提案をいただいのだと思います。文化セクターが、社会との接点を結んでいくやり方として、「社会的処方」を一つのひな型にして、そのあり方を検討する。そして共創の場を作るということを、大学や国や県の劇場がこれからやっていくということですね。本日はありがとうございました。
(text by 平原 礼奈)





