令和6年度「芸術文化分野の手話通訳研修プログラム」レポート3
芸術文化分野の手話通訳研修プログラム(主催:東京都、アーツカウンシル東京)の7回と8回をレポートします。
芸術文化分野といっても幅広く、また、芸術文化とのかかわり方も鑑賞だけではなく、みずからが表現者であったり、企画者、運営者だったりとさまざまです。どの場面においても、だれもが楽しむことができる環境を整えることに東京都とアーツカウンシル東京は取り組んでいます。この手話研修プログラムは、このさまざまな場面で必要とされてきていることも背景に、だれもが楽しむことができる環境づくりのひとつのプロジェクトとして実施しています。このレポートでは、講座の報告とともに、受講生がこのプログラムを通して、なにを学び課題と感じたかについてもあわせて報告いたします。
また、この8回の講座の重要な点をまとめなおした動画を公開しています。こちらもぜひご覧ください。(動画のリンクはページ最後に)
第7回:令和6年11月16日(土)
-
『東京文化会館 リラックス・パフォーマンス』参与観察
-
参与観察体験によって得た知見・感想の共有/飯泉菜穂子
-
ホール・劇場での手話通訳の場面/アーツカウンシル東京事業調整担当課長 駒井由理子
7回目は都立文化施設のうち、音楽コンサートやバレエやオペラといった舞台芸術のホールである東京文化会館の主催事業のリラックスパフォーマンスの参与観察です。(本公演については、文化会館のウェブサイトで確認してください。 ここでいう参与観察とは、その視点にできるだけ近づき、できればその視点になって観察し学ぶことです。今回は、舞台に立ちパフォーマンスを行う「ろうナビゲーター」のYumiko Mary KAWAIさんとsasa-Marieさん、客席にいる手話通訳者、そして、ロビーでお客様対応をする手話通訳者、そして手話を必要とするお客様、そしてその施設で働く人びとの視点も含みます。チケットを購入しそれぞれにコンサート会場に向かうところから講座は始まります。さまざまな視点に立ち、観察、体験してもらいました。
コンサートの終了後は会議室に場所を移し、感想や観察した気づきを発表。受講生からは、ろうナビゲーターのお二人に向けて客席で手話で音情報を伝えている複数人の通訳者の役割分担や、視覚的にも楽しめるようになっている舞台の演出への気づきや質問があり、また字幕提供がある場合の手話通訳の方法に注目していた受講生もいました。
飯泉講師からは、今回の客席にいる通訳者の役割を例に、パフォーマンスするの方への同時通訳とは異なる手話通訳の考え方を、 続いて、アーツカウンシル東京の駒井から、演劇公演や音楽コンサートの制作過程はどのようなものか、場面ごとに求められる通訳業務とはなにかと専門用語の入手方法を教わり講座は終了。
芸術文化分野の手話通訳というと、美術館での手話付きギャラリートークや講演会などで、鑑賞者の前にたつ姿をイメージする方も多いと思いますが、今回のように、手話話者の方が出演者として舞台にたつときのための稽古、また企画会議への参加など、表には見えない場面でも多くの手話通訳者が制作チームの一員となって活躍しています。この7回目の講座は、このようになかなか知ることができない文化施設の現場の様子を垣間見ることにより、受講生が視野を広げる機会となったと期待しています。
第8回:令和6年11月17日(日)
-
当事者からみる美術館全体のアクセシビリティとドーセントーろう美術全体のリサーチ/ゲスト講師 管野奈津美(Re; Signing Project代表)
-
ろう当事者の視点から考える文化芸術とのかかわり方/ゲスト講師 牧原依里(映画監督)
-
ワークショップーろう者と通訳者の信頼関係の構築方法/牧原依里、管野奈津美
-
講座を終了するにあたって/飯泉菜穂子
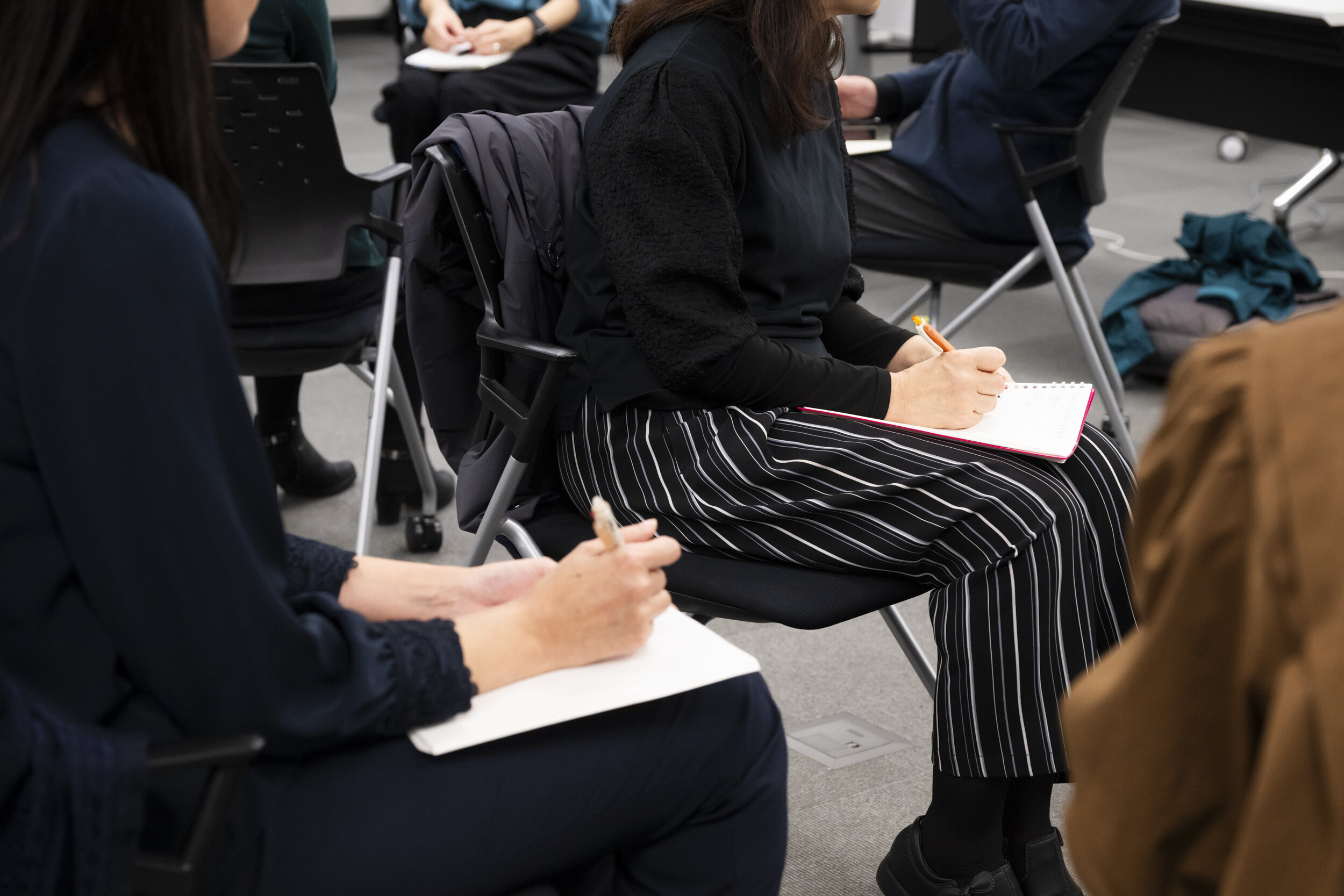
いままで、“言語である手話”や“通訳における等価性”など多くのことを講座の中で取り上げてきましたが、第8回は最後のテーマにふさわしい「当事者性の担保」です。
初めに、管野氏からろう者に関わる今までの出来事やろう芸術の概要やその流れの説明があり、次に牧原氏からは、いま、日本での芸術分野ではろう者の方がどのような活躍があるのか、そしてパリで開催された展覧会「ろう者の歴史」(L'Histoire silencieuse des Sourds)からさまざまな事例の紹介がありました。“過去”から“今ここ”までを短い時間でしたがお二人から学ぶ前半となりました。
後半は、「ろう者と手話通訳者の信頼関係の築き方」というテーマのグループワークです。このワークでの設定は、企画運営や制作者、演出家がろう者であることです。
グループワークのあとは、発表の時間。「○○を知る」として、次々にホワイトボードに書き出されていきます。それは、手話の技術だけではなく、チームが機能していくための心構えも含みます。そして大切なことは、情報をすべて伝え、決定権を本人が持つことというメッセージがお二人から伝えられました。
後半の飯泉講師による最後のまとめは講師と受講生で、「手話通訳とはどんな仕事なのか」をあらためて考える機会でした。「手話は言語である。音声言語とはことなる音韻・語彙・文法をもった言語である」を前提に、「言語」「社会」「文化」、それぞれについて学ぶこと、そして、手話言語と音声言語の通訳である手話通訳とはどのような技能が必要なのかなど、今まで学んできたことを再確認するまとめの回となりました。
受講生からのアンケートから、受講生は何を学び、そのことを今後に生かして活躍していただけるのか、課題は何かを紹介して、令和6年度のプログラムの報告を終わりにいたします。
<受講生によるアンケートから>
・文化、芸術分野で活躍されているろう者から直接事前準備のことや求められる通訳像について教えてもらえた。
・ワークショップも取り入れられており、体験しながら学ぶことができた。
・今まで学ぶことができなかった資料の読み方、打ち合わせの仕方、自己検証など学ぶことができた。
・今まで読み取りについて苦手と漠然としていたが、ポイントを意識して練習できるようになった。
・現場で活躍しているろう者の想いや考え、ろう者を取り巻く環境などアップデートすることができて通訳技術向上への意欲を再燃させることできた。
・個人的なフィードバックをもらう貴重な機会があった。
・講師より学ぶのみではなく、受講者同士で意見交換を行い学びになった。
・この分野での現場での経験が圧倒的に少ないことによる翻訳しきれなさを課題として感じた。
・養成講座並みに毎週あってもよかったと思うくらい、あっという間に終わった感じした。
・他通訳者との連携方法等の知識が不足していることが今後の課題。
・芸術文化関連で活動されている方々とのつながりがないことや情報収集力が乏しいことが課題。
レポート:アーツカウンシル東京 事業調整課


